|
| もっとも代表的でよく使われる「ベースを下降させる」手法から解説していきます。 同じコード進行上にどのような「ベース・ライン」を当てはめられるか考えてみます。もともとのコード進行の響きと比較しながらチェックしてみてください。同じコード進行とは思えないくらいの変化があります。 非常に効果的なのでいろいろな「ベース・ライン」を探してみると良いでしょう。 |
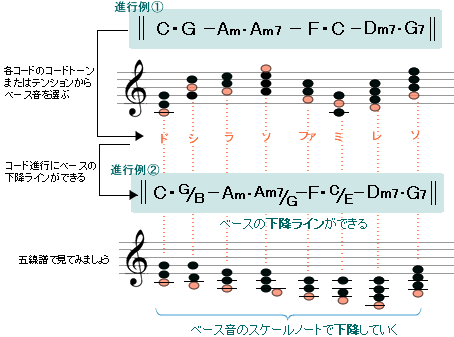 |
| ペダル・ポイントを使用する ベース音を一定に保ちながらその上でコードを進行させていきます。 一定のベースの上でコードが“すべる”ようにチェンジしていくので、“モード”を連想させるような独特の雰囲気になります。 進行例3のコード進行のベース音をA音でキープして進行例4を作ってみます。 雰囲気の違いを感じてみてください。 |
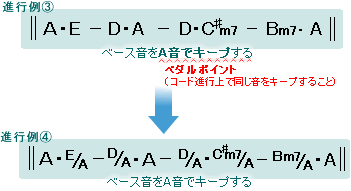 |
| 次に紹介してみたいのが『メロディの始まる音による雰囲気の違い』です。 曲というのはコード進行のみで出来ているはけではなくて、“メロディ”が乗って初めて完成するわけです。 “メロディ”がもっとも大切な要素と言っても過言ではないでしょう。コードに対して、そのコードの中の「どの音」からメロディを歌い始めるかによって、同じコード(またはコード進行)上でもまったく違うメロディを作ることができるのです。 おもしろいアイディアですので、ぜひ声に出して試してみてください。 私自身もメロディの「マンネリ」を解消するためによくこの方法を用いています。 |
 |
Cコード(トライアド3和音) |
 |
POINT! C( I )コードに対して、次の音からメロディを歌いはじめてみてください。 すべての音、それぞれのカラーをもったメロディができるので試してみてください。 |
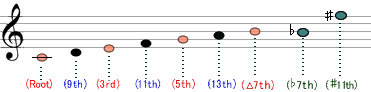 |
|
| 最後に簡単ですが『アナライズ(分析)』について解説しておきます。 人の曲、過去の名曲などを自分なりに分析して、そこからたくさんのアイディアをもらって自分の曲作りに活かしていくことは非常に大切な作業だと思います。その「やり方」「書き方」などを簡単に紹介しておきますので参考にしてください。 |
|
| 手順1では、曲全体の構造やサイズをチェックします。
手順2では、手順1の譜面に書き加える形で各コードの役割りを細かく分析していきます。 ↓クリックすると手順ごとの譜面を表示します。 |
| 手順1の譜面に書き加える形で手順2のように各コードの役割りを細かく分析していきます。 「トニック」、「サブドミナント」、「ドミナント」、「セカンダリー・ドミナント」、「サブドミナント・マイナー」、「ドミナント・モーション」、「トゥ・ファイブ」、「転調」・・・・。すべてのコードをチェックしていくと、その曲のポイントや「カギ」になるコードの使い方などを発見できるはずです。理論に当てはまらないけどもカッコイイ、パターンやコードもどんどんメモして曲作りのネタを増やしていってください。なるべくたくさんの曲を分析してみると良いでしょう。 |
| ●まとめ これで『アコギで作曲〜簡単コード進行理論』は終了です。『フレットで覚える音楽理論』のコーナーと合わせて総復習してみてください。根拠のあるしっかりとした知識を身に付けて、みなさんの湧き出る「インスピレーション」を素早くイメージ通りの形(曲)にして、納得のいく曲をたくさん作ってください。 次回からは、すべての基本となる『メジャー・スケール』について解説していきたいと思います。お楽しみに。 |
| 第9回へ ギターにハマる!INDEX ギター検索 | |
| ★日本で最大級のギター登録本数と加盟楽器店★ ↓ギター検索はJ-Guitar.comの楽器サーチで↓
|
| Copyright:(C) J-Guitar.com All Rights Reserved. |